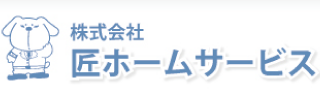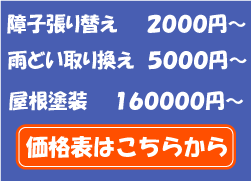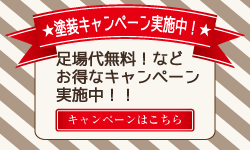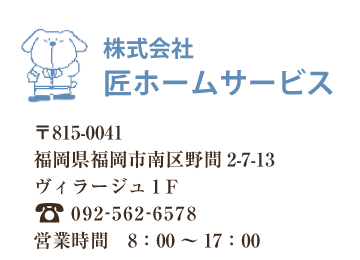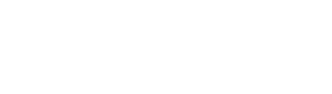タイル
日本には6世紀の仏教伝来とともに寺院の装飾用として伝わりました。
建設資材の1つで、壁や床の保護、装飾用に多数張りつける板状の素材です。
日本の建設資材の中で、産業集積地のある建材は珍しく、
歴史と伝統のある地場産業です。(岐阜県の多治見市・土岐市近隣)
一般にタイルといえば、陶磁器製のものを指すことが多いのですが、
素地の質や吸水性により「磁器質タイル」「せっ器質タイル」
「陶器質タイル」の3タイプに分かれます。
タイルメーカーでは、タイルの適した用途に応じて、
屋内の水廻りや壁、床用、屋外の壁用、
屋外の床用などに分けている。
気温の変化の影響を受ける屋外の外装用のタイルには、
吸水性の低い磁器質タイルやせっ器質タイルが使用されます。
「磁器質タイル」
石英・長石・粘土などを、高温(1300℃前後)で焼かれたタイルで、
吸水率が低く(1 %以下)、水をほとんど吸わないタイルです。
硬くて丈夫なので、気温の変化や、風雨にさらされても、
割れが起きにくいのが特徴です。透明感のある美しさもあります。
素地は緻密で硬く、たたくと清音(金属音)を発します。
外装タイルや歩行頻度の高い床タイルなどに使用されています。
「せっ器質タイル」
長石・粘土などを、1200℃前後で焼かれたタイル(焼成)で、
陶器質タイルのような透明感はないものの、素地は硬く、
耐久性が高いのが特徴です。
磁器質タイルと同様に吸水性も低い(5%以下)タイルです。
素焼きの素朴な色むらを生かした外壁タイルなどに使用されています。
「陶器質タイル」
陶土や石炭などを、1000~1200℃で焼成したタイルで、
吸水率22%以下で吸水性の高いタイルです。
陶器質タイルは多孔質で吸水性が高いため、
磁器質タイルなどに比べると耐久性が落ちます。
主に内装材として使用されています。
タイル特徴① 吸水性が低い
防水性に優れ、水がかり部に使用されることが多い。
吸水率が低いほど磁器の性質を現すことから、
かつては、吸水率だけで分類されていましたが、
技術発達もあり、吸水が高くても磁器の性質をもつものや、
低くても陶器のような性質をもつものがあり、
かならずしも吸水率だけで、磁器タイル、陶器タイル、
せっ器タイルと、判断することは難しくなりました。
タイル特徴② 耐久性が高い
タイル自体の耐候性・耐久性は高いのですが、
タイルサイズが大きかったり、施工が悪かったりすると、
下地の強度が落ち、剥離してしまう可能性や、
目地が劣化することがあります。
モルタルと混ぜられる接着剤の性能や、施工法の向上が行われ、
事故は減少傾向にありますが、工事を頼む会社選びも大切です。
美観性を保つためにも、汚れがつきにくく、
汚れが落ちやすく、目立ちにくいものを選ぶと、
その後のメンテナンスが容易でしょう。
光触媒コーティングで防汚機能のついた、
機能性の高いタイプもありますので、
合わせて相談すると良いでしょう。
デメリット
- イニシャルコストが高い
- タイルが大きいと剥離しやすい